吉田兼好の『徒然草』──
この古典を久しぶりに手に取ったのは、
前立腺癌ステージ4の告知を受けた後だった。
時間の流れ方が静かに変わり、日々の感じ方が少しずつ深くなる中で、
私は「いま一度読み返したい本」を探すようになった。
これまで一千冊以上の本を読み歩いてきたが、
その旅を私はいつの頃からか“せきがくの旅”と呼ぶようになった。
そして今、その旅路の中で、徒然草がもう一度、
最も近くに置きたい本として戻ってきたのである。
■ なぜ、いま徒然草なのか
徒然草の冒頭、「つれづれなるままに」で始まる一段は、
中学生のとき暗唱した記憶がそのまま残るほど、
どこか懐かしく、どこか優しく響く。
「心にうつりゆく由なしごとを、そこはかとなく書き付くれば──」
言葉には不思議な力がある。
若い頃には理解しきれなかった“静かな深さ”が、
今の私ははっきりと胸に沁みてくる。
病を抱え、時間の有限性を直視するようになると、
人が人生のどの段階で、どんな言葉に耳を傾けるのかは変わるものだと痛感する。
四季の移ろい、人の心の機微、日常の美しさ、孤独の味わい──
兼好の言葉は、現代を生きる私たちの心に驚くほど寄り添ってくる。
■ 心に残った五つの段
徒然草には243段が収められているが、
その中から特に心に深く刻まれた五つの段を紹介したい。
◎ 第七十五段:つれづれわぶる人
「何の用事もなく独りでいる時間こそ、人が最も豊かに生きる瞬間である」
兼好はそう語る。
静けさの中にある自由。
予定も義務もない時間が、どれほど贅沢なのか。
忙しさこそ価値と信じがちな現代に、
この言葉はひとつの警鐘のようでもある。
私自身、今は独りで過ごす時間がこれまで以上に深く愛おしい。
「何もしていない時間」こそ、自分の心がいちばんよく見える。
◎ 第十二段:同じ心ならむ人
「心の合う相手と語り合うことは、何よりも尊い」
兼好はこう言う。
しかし、現実にはそんな相手は多くない。
むしろ“本音で語れる人”は、人生の中でほんの一握りだ。
だからこそ人は、相手の顔色をうかがい、
場を整えるために余計な気配りをしてしまう。
そのときふと湧く「孤独感」。
兼好が生きた時代も、いまの私たちと変わらない。
人は、いつの世も孤独という影を連れて生きている。
◎ 第十五段:いづくにもあれ
「ちょっとした旅が、心を目覚めさせてくれる」
ほんの数時間の外出でもよい。
いつもと違う景色に身を置いた瞬間、
心が軽くなる経験は誰しもあるだろう。
“旅”とは距離の問題ではなく、
心の置き場所を少し動かしてみることなのだ。
◎ 第十九段:折節の移り変はるこそ
季節がめぐるたびに、人は人生の節目を思う。
春の芽吹き、夏の陽光、秋の落葉、冬の静けさ。
四季の移ろいには、どこか“あわれ”が宿る。
「変わる」ことを恐れるのではなく、
「変わる」からこそ美しいのだと教えてくれる。
◎ 第百八段:寸陰を惜しむ人なし
「時間の価値を見つめ直せ」という兼好の言葉は、
今の私にとって非常に重い意味をもつ。
時間とは、残りを意識したとき、初めて本当の重みを帯びる。
終わりがあるからこそ、いまが輝く。
この段を読むたびに、私は胸の奥がぎゅっと引き締まる。
■ 兼好が語る「無常」は、決して悲しみだけではない
徒然草の根底にあるキーワードは「無常」である。
無常とは、「すべては移ろう」という考え方。
一見すると冷たく、厳しく、寂しい響きに聞こえるかもしれない。
しかし兼好は、無常を“救い”として捉えていた。
著者はこう述べている。
「兼好は、人間の力ではどうにもならないさまを無常と呼んだ」
無常とは、どうにもならないから諦める、という消極的な姿勢ではない。
むしろ、人が“いまをどう生きるのか”と向き合わせてくれる
前向きな思想である。
「変わっていくすべてを受け入れるとき、
人生はやさしくなる」
そんな兼好の声が聞こえてくる気がする。
■ 末期癌の告知──“いま”という瞬間の重さ
私は前立腺癌ステージ4の告知を受けた。
死がまだ遠かったころ、無常という言葉は
どこか哲学的な、抽象的な響きに感じていた。
しかし今は違う。
無常は、日々の息づかいにまで入り込んでくる。
「確定した死」
「しかし、いつ訪れるかは分からない」
このふたつを抱えて生きると、
人は一瞬一瞬を手放しでは過ごせなくなる。
朝の光に心が震え、
風の匂いにも理由なく涙が込み上げることがある。
痛みではなく、
「生きている」という感覚が極めて鮮明になるのだ。
■ 無常は、恐れではなく“優しい受容”を教えてくれる
無常の思想に触れて思うのは、
「すべては移ろう」ことは、
決して絶望を意味しないということだ。
むしろ、無常を受け入れるほどに、
人は余計な執着を手放し、
いま目の前にある人、物、景色、時間を
心の底から大切にできるようになる。
病の宣告という現実は厳しい。
しかしその中にも、
静かに寄り添ってくれるものがある。
それが徒然草だった。
■ 私の仕事の終焉に向けて
今、私はひとつの仕事の終わりに向かっている。
集客ゲートという仕組みを仲間と築き、
多くの工務店の未来に役立てることを願ってきた。
「自分は誰の役に立てただろうか?」
「何を残して逝けるのだろうか?」
そんな問いが、時折胸に浮かぶ。
徒然草はそんな私の気持ちに静かに寄り添い、
「いまやるべきことに心を向ければよい」
と語りかけてくるように思う。
完成まであと少し。
やり抜きたい。
そう思う気持ちが、以前より強くなっている。
■ 徒然草は、私の横に置いておく本
徒然草を読み進めるたび、
兼好が見ていた世界が少しだけ分かる気がする。
人はどこから生まれ、どこへ行くのか。
生とは何か。
死とは何か。
すべての問いに答えはない。
しかし、答えがないからこそ、
私たちは生きる意味を探し続ける。
徒然草は、そんな“探す旅”の伴走者のような存在だ。
■ まとめ──無常という光
著者は、兼好について
「平常心で無常と対座した人」と記している。
私もまた、
無常という光に照らされながら、
残された時間を静かに、そして丁寧に生きていきたい。
悲しみだけではない。
終わりがあるからこそ、
今日の一瞬が愛おしくなる。
徒然草は、
過去と今と未来をつなぐ、
私にとっての“心の杖”のような一冊である。
ボアソルチ。
#徒然草 #吉田兼好 #無常 #日本の古典 #読書ブログ #人生を考える #哲学の言葉 #前立腺癌 #生きる意味 #心の旅 #せきがくの旅 #生き方のヒント #一瞬一瞬を大切に
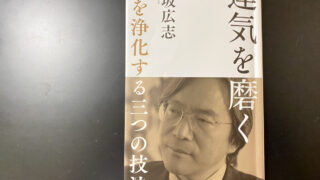
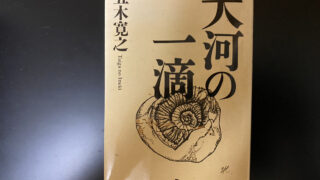
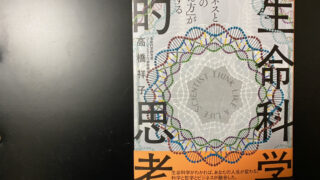
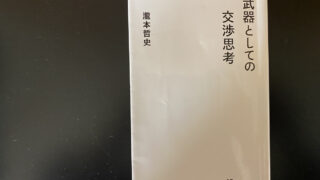
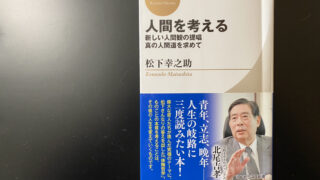
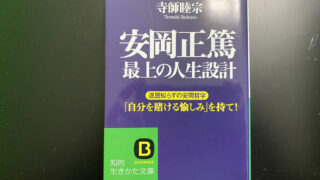
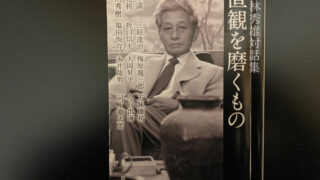
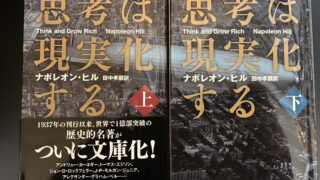
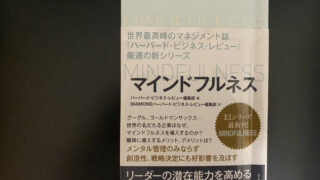
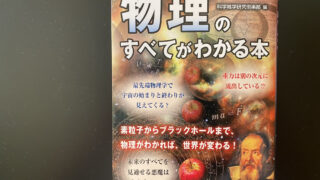
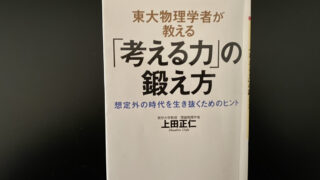
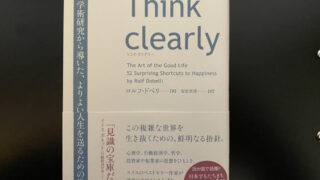
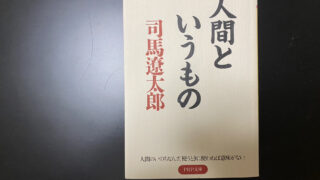
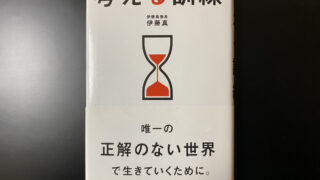
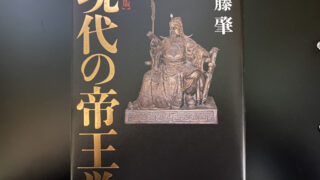
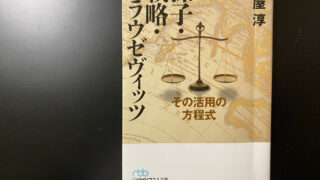

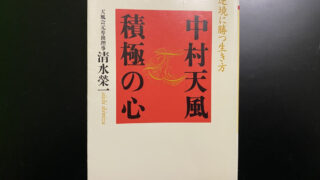
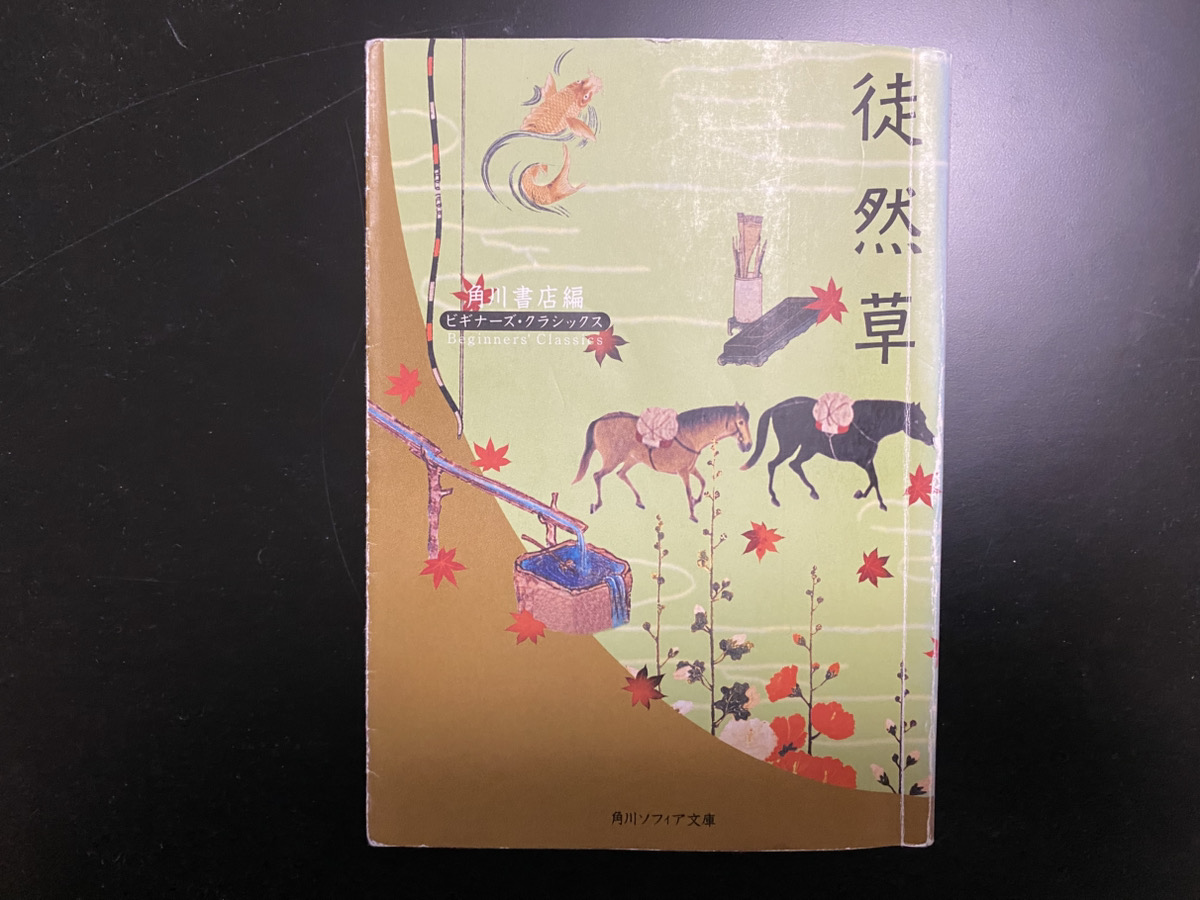
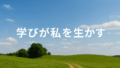
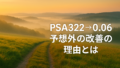
コメント